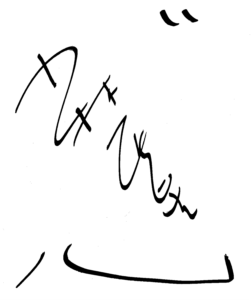
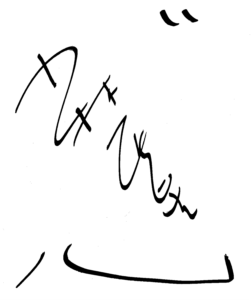
プロジェクトスタート!
大ニュースでーす。
ぼくの仕事上の話ですが、「一流作曲家(音楽家)の講演」という企画を提案してたところ、
ついにプロジェクトがGoになりました。
プロジェクトリーダーはぼくでーす。
講演者はまだ未定です。これから人選しますが、
小沢征爾さん、渡辺貞夫さん、坂本龍一さん、小室哲也さん、中村正人さん、
松任谷正隆さん、小田和正さんなどが来てくれるといいなあと思ってます。
(本気かー!?)
全部交渉じゃ!!あたって砕けろー!
講演は、一般公開できるものでは無く、報道陣シャットアウトで行いますが、
(そうじゃないと、生のお話が聞けないんです。)
企画から、交渉、講演内容の打ち合わせ、講演の実現まで、プロジェクトの
一部始終をドキュメンタリーで公開しちゃおうかなーと思ってます。
(差し障りがある内容は内緒です。)
さて、どうなる事やら?
学校の先生の講演で終わったりして・・・(笑)
Jリーグチェアマンの講演は実現した! この企画もなんとかするぞっ!
一流作曲家講演プロジェクト その2
講演予定は、12月頃に決定!
スタッフの募集を各部署にする事になりました。
総務課は各所属長経由で来週・・・なんてかったるい事を言ってたので、
あちこち走り回って、やりたいやつをかき集めてしまいました。
「ドリカムとか、小室哲也呼ぶんだよ」と大口たたいて・・・
男性3名、女性1名・・・・みんなミーハーだなあ。(笑)
やっぱり、スタッフはやらされより、やりたいやつじゃなくっちゃ!
さて、いよいよ学校の先生の講演で済ますわけには行かなくなった。(汗)
一流作曲家講演プロジェクト その3
スタッフメンバーようやく正式決定。
自分でかき集めたメンバーが二人正式にメンバー化。
女性スタッフは、正式メンバーにはなれなかったけど、
お手伝いしてくれるそうで。ドリカムなら絶対ついてくるって。(笑)
それと、広報担当にデザイン関係が得意な方に参加していただけました。
あとは、一番重要な窓口係に話をつけて。
ルートだけは開拓してくれて、あとは自分で交渉に行く事になりました。
さて、どう交渉しようか?その前に誰と・・・?
阪神の野村監督はだめでした。(おいおい作曲家か?)
一流作曲家講演プロジェクト その4
企画書と日程案書いてスタッフ召集しました。やっと。
講演内容の検討、交渉、広報、会場セッティング、司会。
やるこたーいっぱいあるなー。
いちおー担当者決めて押しつけてしまいました。(笑)
次に、何講演してもらいたいか・・・
ずばり、多くの若者の心をとらえる曲をどう作るのか??
これは、だれも異論を挟む余地無し!
でも、詳しい話しになったらスタッフは予想以上に燃えてて大揉め。
流行る曲はマーケティングのうまさだろとか。
でも、ぼくが聞きたいのはちょっと違うんだよね。
マーケティングだけで、聞く人のどぎもを抜く曲ができるかー!
みたいな・・・・・
やっぱ、感性で創造するって言ってほしい。(T-T)
講演者は、ぼくが中村正人さん呼びたいって言ったら、
なぜそうなのかってだいぶやられました。
いーじゃん、ぼくが好きなんだから(笑)
スタッフは、小室さんだとか、
マーケティングのうまさでは、
松元康さんだとか、松任谷由美さんだとか・・・・
結局OKもらえるかわかんないから、かたっぱしから、
アポとってみることにしました。
さーて、どうなることやら。(謎)
一流作曲家講演プロジェクト その5
あ〜、アポとんのも大変だじょ〜
そもそも、どこの誰に連絡したらいいかわかんないし(笑)
総務課の担当にアポたのんどいたら、1ヵ月経っても音沙汰ない(泣)
いろいろ嗅ぎまわったら、○×企画というイベント屋さんに頼むと、
プロダクションとか詳しいんで、引き受けてくれるとの事・・・
で、その○×企画は総務課がよく知っているらしい。
なんじゃーい、そんならすぐ呼んでくれー!
と思って、総務課の担当に電話したら、出張中 (T-T)
いーかげん、いらいらしたんで、
こーなったら、プロダクションにダイレクトに電話してやる!
と思って、ドリカムのプロダクション、エムエスアーティストの
電話調べて代表にいきなり電話しました >チャレンジャー!
・・・実は緊張して、かけるまで2〜3回たばこ吸いに行った(笑)
で、かけてみたらなんか女の人の美しい声で、ほっと一安心。
不慣れであうあうしてたら、(-_-;) 親切にいろいろ教えてくれました。
でもドリカム担当のディスクは、現在ツアー中でいませんでした。
そりゃそーだ、明日からワンダーランド、福岡ドーム公演の真っ最中だし
(東京公演行きてーぞ!)
というわけで、門前払いはされなかったけど、
講演なんか引き受けてくれるかどうかは、ツアーから帰ってくるまで不明です。
まあ、担当ディスクの名前と電話番号を教えてもらったので、
大進展でしょう・・・・
なんでーい!自分でやりゃすぐじゃねーか(怒)
一流作曲家講演プロジェクト その6
ちゅどどどどど〜〜〜〜ん(爆死)
ドリカム、講演断わられました。(T-T)
ま〜99%予想してたけど・・・・・
CDのレコーディングと、ソレに関する活動以外
してないそうです。
う〜ん、スーパースターだなー。
今、ラジオもやめちゃってるしなー。
ところで、ドリカムの担当ディスクの方は女性でした。
まあ、ダイレクトに連絡しただけでもいい経験でしょう。
名前と電話番号わかったし。ひひひ
(おいおいストーカーか?)
さーて、次の作戦はどうしようかな〜?
一流作曲家講演プロジェクト その7
も、もしかしたら・・・・・・
ま・ま・松任谷正隆さん、脈有りかも・・・・??
講演経験も豊富だとか。
喜ぶのはまだ早い。
やってくれる事もあるよ、という情報だけ。
現在交渉中。
なにしろ、ミュージシャンに講演しろというのは、
なかなか専門でないだけに難しい事がわかりました。(泣)
一流作曲家講演プロジェクト その8
松任谷正隆さん、スケジュール調整困難・・・・ガクッ
と落ち込む暇も無く、どえりゃー超大物が!!!
小林亜星さんが講演、スケジュールともOKそう /(゚ё゚)\
亜星さんを、寺内貫太郎と思ってる方が多いと思いますが、
作曲をする人にとっては、レコード大賞をはじめ、
各賞をぞろぞろと受賞され、超有名ドラマ、アニメ、CMの主題歌は、
ほとんど亜星さんと言って過言でないし、某音楽学校の学長さん、
日本作曲家協議会理事、日本音楽著作権協会評議員
などなど、神様のようなお方です。
ここまでの悪戦苦闘をまとめると、
講演が得意で、条件さえ整えばやってくださる作曲家、作詞家、編曲家は
小林亜星さん、
秋元康さん、
松任谷正隆さん、
三枝茂彰さん
講演NGだった方は、
中村正人さん、
吉田美和さん、
久石譲さん、
山崎まさよしさん、
奥田民生さん、
小椋佳さん、
来生たかおさん
企画会社に相談したら、嘲笑されて終わった方は、(T-T)
小室哲也さん、
坂本龍一さん、
小沢征爾さん、
渡辺貞夫さん、
松任谷由実さん、
桑田佳祐さん、
小田和正さん、
宇多田ひかるさん・・・・でした。
というわけで、当たって砕けろだったけど、芸能人にこういう事頼むのはどーしたらいいか、ちょっと見えてきました。
ん〜、音楽家リンク集になったぞ。(笑)
一流作曲家講演プロジェクト その9
こばやしあせいさん O K ! 日程Fix
さっそく、企画書手直し、講演内容調整、会場予約手配、
プロフィール入手してPR文書、ポスター、案内の依頼、
音響設備の調査、会場下見の準備、スケジュール作成、
予算の調整、備品の準備・・・・・後なんだっけ?
決まると嵐のようだー!
一流作曲家講演プロジェクト その10
企画会社の方と講演会場の下見。音響設備、照明、控え室のチェック。
当日講演終了後に亜星さんを、お食事会にでもお誘いしようと思ったら
どうやらスケジュールがあるらしい・・・・残念。
講演会PRポスターに使える写真をお願いして
肖像権許可のある写真をいただきました。
HPに使用のご相談もして、商用でないという前提で許可をもらいました。
さっそく使わせていただきます。(やったー!)写真入ると、やっと実感湧いてきた! (笑)

写真提供:(株)ザ・カンパニー
小林亜星さん対談トップへ
一流作曲家講演プロジェクト その11
いよいよ講演の内容について亜星さんと調整する事になりました。
基本的なお話しは幾つかお持ちなので(さすが)どれか選んで、
要望があればアレンジしてくれるそうです。
この際だから、聞きたい事はみんな聞いてしまおうと、
プロジェクトメンバーの要望をみんな入れて書いてみました。
これ全部まじめに答えてくれたらえらい事だけど、まずはお願いしてみます。
<講演内容希望>
「100%感性の商品を作るってどんな事?いい曲、売れる曲、人を感動させる曲とは、どうやって作るのか?」
1、音符
ネジの長さ、太さ、位置は、強度、他の部品との干渉、工具の形状等から
計算で設計できる。
音符の音程、位置、長さ、強さ、は作る人の勝手(感性)に思える。これをどの様な判断基準で決定し、最終的に販売する曲とするのか。
音楽理論で設計できるものなのか?
2、曲
・曲とはどの様なプロセスで作って行くものなのか?
曲想、構成、楽節、フレーズ
・感性に訴えかける商品の作り方
たとえば、何かしら「グッ」っと来るものが無ければ、
お客さんはCDを買ってくれないし、Liveにも来てくれない。
何かしら「ちょろっ」と感じるフレーズの取っ掛かりをつかんだ場合、
それをどのようにして「グッ」っと来るひとつの曲に仕立ててゆくのか?
こういうのがイケるんだ、と言うのが経験的にわかったときがあるのでしょうか。
・売れる楽曲と作りたい楽曲、商売の面と芸術の面、
といった二面性があると思います。
使い分けているのでしょうか、それとも両立するのでしょうか?
・曲先・詩先について
歌曲の場合、「メロディーが先に有って詩を付ける」場合と「詩が先に有ってメロディーを付ける」場合とがあると聞いた事がある。
更に、詩もメロディーもまだ無い状態で、曲全体のコンセプトやイメージだけ先に決まっている場合もあると聞いた事がある。
その様な詩やコンセプトが自分の感性にいつでもぴったり合うとは限らないと想像されるが、その様な場合、どのように折り合わせるのか?
作って行くうちに、当初のコンセプトやイメージと異なるものになってしまうことはないのか?
3、編曲
・基本編成(リードボーカル、ベース、ドラム、コード楽器)以外のパートは、
どのように決定していくのか?
・曲のアレンジについて
同じメロディーであっても、アレンジ違いで全然違う
曲のようになることが多いようだが、作曲をする際に
予め何通りかのアレンジを想定しているのか?
アルバムバージョンとか、シングルバージョンとか、
Remix バージョンとか・・・
もしそうなら、どのようにアレンジを決めるのか?
・歌手や演奏家などの効果的な活かし方について。
たとえば、この歌手でなければ表現できないと言うものはご自身の中ではあるのか?
「調査、計算でできるのか?」
4、音楽におけるマーケティングとは?
・タイムリーな商品開発
商品開発風に考えると、今現在の流行に乗っかったものを今作っても、
売り出したときにはすでに乗り遅れているわけで、そのためには何らかの形で、
先を見越した曲作り(商品開発?)をしなくちゃならないと思うのですが、
亜星さんはどのようにして、Hit曲を作ったのか?
・ターゲットの絞り方
市場(買ってくれる人?)に受け入れられる路線の、自分の中での決め方。
購買層(顧客???)に受け入れられたいものを作るときの狙いの定め方
なんてあるのでしょうか?
曲作りのためにマーケティングする方もいるようですが…
5、感性無しでどこまでできる?
曲を作って行く過程で感性によるもの以外に、慣習、やり方、理論、判断基準は
どのくらいあるのか?
自動作曲するソフトがあるが、なぜ泣けない?
「努力すべき事は?」
6、どのようにして、すばらしい曲が作れるようになっていったのでしょうか?
・苦労
・ターニングポイント
・クリエイティビティは後天的に身に付くのか?
付かないとするとどうやって補っているのか?
・感性の磨き方
Hitメーカーとして、所属事務所から、あるいはクライアントからプレッシャーも有るかとは思うが、長い間イケる曲を作り続けるために、何らかの形で意識して(努力して)いることは有るのでしょうか?
一流作曲家講演プロジェクト その12
かっこいいポスターもできて、ついに聴講者募集開始!
と思ったら、当日別件でスタッフ約2名アメリカへ出張。(泣)
えーい!どーすんじゃー?
みんなおれがやりゃあいいんでしょ!
亜星さんも、裁判がえらい事みたいなので、こちらの要望にはあんまり応えてもらえそうにないし・・・・ ん〜〜〜、まあ、どーにかなんでしょう。(笑)
一流作曲家講演プロジェクト 本番
本日小林亜星さんの講演会をついに実現しました!
亜星さんは、予想以上に素晴らしい方で、お忙しいところを、こちらの要望に全面的に応えていただく事ができました。大変物腰が低くて紳士であるし、なにしろ、お話しには感動いたしました。本当に聞きたかった事以上の事が聞けて、目からうろこ状態です。
急遽手持ちの演題をやめて、ぼくの書いた質問に応えるお話しをトークショー形式でやっていただけました。
ぼくが相手じゃトークショーがうまくいかないんで、アナウンサーの稲見幸子さんに急遽来て頂いて(すげー美人だー!)時間を延長してたーっぷりお話しをしていただけました。
こっちはどたばたしててスタッフも不慣れなもんで、亜星さんには失礼をしてしまったかもしれない・・・・(汗) 最後お見送りに間に合わず帰してしまった!(ギャー)しかし、サインと、2ショットの写真はしっかりゲット!(笑)
思い出せばいろいろ冷や汗ものですが、なんとか終わりました。
亜星さんはじめ、スタッフの皆様ありがとうございまいした。
トークショーの模様は貴重なのでぼちぼち紹介してみようと思います。
このページは、僕が作成した「亜星さんに聞きたい事」をベースにして、 小林亜星さんと聞き手の稲見幸子さんで、トークショーを行なっていただいた内容をメモしたものです。 ご本人が話した言葉そのものではなく、省略、要約をしております。 場合によっては聞き間違い等もあるかもしれませんのでご了承ください。

写真提供:(株)ザ・カンパニー
稲見
そもそも亜星さんが作曲家になられたきっかけというのはございますか?
亜星
そうですね。ぼくはあのー、うちにピアノが無くて、昭和7年産まれなんですけど
今年もう8月で68になっちゃうんですけども。この頃ピアノがあるうちなんてそんなに・・・
私東京生まれの東京育ちでしたんで・・・・、そんなに無かったですね。
今600万台もピアノが余ってて、埃かぶってだれも弾き手が無い。
だけどまあ、音楽好きだったんですが、少年時代はハーモニカぐらいしか吹けなかったんで
大した作曲家じゃないんですけども。
中学一年の時終戦になって、米軍がやってきましてね。アメリカの音楽がどっと入って来たら
戦時少年で全然ジャズとかそういうの知らなかった。まだロックは産まれてませんでした。
それでたちまち、しびれてしまいまして、中学生頃からバンドやりまして。まあ、その頃
バンドやってると不良少年っていうんですね。非常にやな思いしましたけどね。
その時はギターやってましたけど、大学の一年頃はビブラフォンって楽器をやって、
それで、朝霞のキャンプに来てました。
稲見
それじゃいろいろな楽器にたずさわっていらっしゃったんですね。
亜星
まあ、そうたいしてうまくないですけども・・・・。それであの、就職もしたんですけども、
一応、落第しないでカスカスで学校出てから、2年ぐらい勤めましたけどね。
どうも向いてないな。いろいろ・・・やってみてその頃は非常に悩みまして、
まあ、音楽がやりたかったんで、学校の頃から作曲は先生に習ってたんですけども、
ま、何人かの先生に習いましたけどね。
何でも、好きでやってる人と、あんまり嫌いじゃなくてやってる人と競争すると、
まず、好きでやってる人が勝ちますよね。
いやいやながらやってると、どうしても勝てないので、じゃあ自分で好きな事で
やるしかないな。やっぱり、音楽で飯食うしかないな。
趣味としてやって行こうと最初思ってたんですけど、まあ、親が大反対で色々苦労した。
ま、そんなんで、最初先生のお手伝いを・・・だんだんこの業界に入ってしまいました。
24の時からですかね。もうだいぶ経ちましたね。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
もう何十年というキャリアになられるわけですね。
その中でもほんとに多くのヒット曲を生み出されているわけなんですが、いわゆるですね。
いい曲、売れる曲、そして人々を感動させる曲というのは、
どのように生み出されていらっしゃるんでしょうか?
亜星
そうですね。全部ね、あのー、曲を作る時、私は音楽監督ですけど、歌を作る場合に絞って言うと
歌っていうのをね、あのー、音楽だと思っちゃう人が多いんですね。音楽家にも。
ところが、歌っていうのは音楽だけじゃないんです。まー、詩という文学的要素があるでしょ。
それから音楽ももちろん、詩と音楽それと歌い手というパフォーマーがいますから演劇的要素ですね。
文学、演劇、音楽の合体した、何か他のもんなんですね。それを理解しないで音楽だけだと思って
作ると、だいたい失敗しちゃうんですね。
だから、まーそうゆう、3つの結合した違うジャンルのもの。
人を感動させるっておっしゃったのは、確かに感動してもらうのが一番大事で、
そうね、それはねー、あのー、ぼくなんかが気がつくまでは・・・・ま、アレンジャーも最初
やってましたんで、ほんとその仕事を4〜5年やったですかね。NHKの番組持って。
自分の音楽番組で毎週仕切って。夜の調べって番組やってたんですけどね。
編曲の仕事ばっかりやってるとなかなかね、メロディー作んのへたになっちゃうんですね。
先ほどおっしゃった(スタッフが)左脳の方ばっかり使っちゃうんで。
人を感動させるっていう事は、編曲によって感動する事ももちろんあるんですけど、
感心させるようになっちゃうんですね。感心させるっていうのは、けっこうやさしいんですよね。
でも、役者でも感心させるのは専門家と違うと言ってね。自分で考えてきて煙草に火つけながら
喋ったりして、お前なー、感心するのはいいけど感動させられるかっていうのは別物で、
ま、感心させられるほどの技術が無いと感動も難しいのかもしれないけど。とにかく、
感動させられるって事が一番難しくて、ま音楽もそうなんですね。だから、ぼくも音楽学校の
先生してるもんですから、みんなよくね、生徒なんかも、自分の知ってる事を全部ね、
俺はこんな事まで知ってるぞってのを、書いてくるんですね。
ぼくもね、自分が先生にならってる頃それが一番怒られましたね。
どうしてもね、人を感心させようとしてね、
俺はこんな事まで知ってんだって事をねやってくんですね。
稲見
でも、普通の人間はそういう方向に走ってしまいますよね。私もそうなんですけども。
亜星
ま、そういう人多いですよ。今の作曲してる人もね。
それは、感動の方が難しくて感心はやさしいんですよね。知識と、勉強すれば。
勉強して、なかなか物事は身につかないですよね。私いつも言うんですけどね、生徒に。
物事は身につけなきゃいけない。変な話だけど、溺れるっていうような、ほんとに好きで好きで
それに溺れないと物事が見につかないんで。勉強しようとしてやってるうちはだめですよね。
そんなような事を言ってる、確か役者がいるんですけど。物事の理解っていうのは、
勉強じゃ身につかないですね。それが好きで好きで、道楽になんないとね。
だから、いい先生っていうのはね。こんなに面白い学問は無いぞと。例えば物理の先生でも
なんでも、ありゃ道楽でやってんですね。医者でも。もう面白くてしょうがないからね、
もう夜も寝ないでやるわけですよ。
だから、生徒に面白くもない講義をしてね、勉強する気なくしちゃうのはね、一番悪い先生で、
一番いい先生っていうのはね、こんな面白いものないだろっていう事を解らせて、相手は道楽に
なっちゃう。そうなるとね、もう教えなくたって自分でやりますからね。
まあ、横道それちゃいましたけどね、道楽じゃないとだめだなあ。
人に感動を与える事もできないですね。私も今まで、これ道楽だからやって来れたんで、
その事が好きだって事が一番大事ですね。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
亜星さんご自身の作曲活動というのは、100%亜星さんご自身の感性で作られているのか、
それとも、何か計算されて?
亜星
いや、計算はね。計算からは、何も作れないですよ。
感性って言うとちょっとオーバーでね。感性って言葉は、流行ってるけど。ん〜、とにかく、音楽はね、目的じゃないと思うんです。
手段であって、何かのための。音楽は何の手段かと言うとやっぱり、生きててよかったな〜とか、なんか、そういう心。優しい心とか、素晴らしい勇気とか、そういう心を与えるための手段が音楽とか、絵でもそうですけど。みんな手段だと思うんですね。
だから、手段だけじゃどうにもなんないんで、与えるものが無かったらね、コンピュータでいくら曲作って出来た出来たと言っても、その伝える目的が無くてね、作ってもしょうがないんで。音楽自体は、どんなベートーベンだろうがバッハだろうが手段なんですよ。
人間っていうものは素晴らしいって事を伝えるためのね。
全部そうだと思います。だからそれを間違えちゃうとね。それがないものを作っても何にもなんないわけですね。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
じゃ亜星さんは人を感動させるために、手段で伝えるために、ご自身はどういった努力、意識を日々の生活の中でされていらっしゃいますか?
亜星
そうですね、それはちょっとね〜。あんまりいい・・・・ある程度不良なのかな。あの〜やっぱり自由な精神っていうのが一番ね、大事だと思いますね。
あらゆる事に自由であるって事ですね。自由を失ったら、人間として伝える事が何であるかって事がわかんなくなってきちゃう。それとね、その自由を無くさないためには、いくつかあります。私なまいきですけど、そういう事考えるとですね、よくこういう夢みるんですよ。どっか、変な林んなか、森ん中入っていきますとね、もう、草むらん中にね、なんか水が湧いてる所がでてくるんですね。そこに、蚋かなんか蚊が、藪蚊がぶんぶんしてそんなような所にね、誰も行かないような泉みたいのがあってね、そこに行くとなんか赤鉛筆が浮かんでたり、変な夢なんですけど、何回も見る。
やっぱり人をね・・・・子供の頃から、子供の頃たとえば、大きな木を見て非常に感動して涙がでたみたいな経験を普通無くしちゃうんですね。忘れちゃう。それを一生持ちつづけるっていうのが大事で、そこはもう人を寄せ付けないで、そこはもう自分の秘密の場所ですね。
そういうとこを確保しとくってのがけっこう大事な事で恥ずかしいんですけど。すごいエゴイストの部分がないと、それが守れない。というのがあるんですね。
それと自由であるって事はね、やっぱり自由を無くすって事が非常に人間としては物をクリエイティブにできないって事の一番原因になるんで、ただの生活者になっちゃうと無くしちゃうんですね。たとえば初恋の人っていうね、まあ初恋じゃなくても男性だったら女性に、君を幸せにするよって約束した時から自分が自由を売っちゃって、そのために生活者になっちゃうんですね。理想も自由も無くして、それで毎日、なんとなく絶望したりなんかするうちに、一生を送るような、生活者になってっちゃうんですね。
そうなっちゃうと、クリエイティブな発想が出てこなくなるんじゃないかなと思いますけどね。その、自由がなくなっちゃう。それはその女性のために自分を捧げて自由が無くなる。だからまあいいや、とも思いますけど、だけどそんなことやめますよとも言えないし。(笑)、まあ、素晴らしい事なんで、だけど自由をなくす。だから、ある程度不良的になっちゃうのかな。と、思いますけど。
稲見
じゃあ、ある意味であまり家庭を省みないタイプの方が、こういった人を感動させる・・・
亜星
そういうと、(笑) 非常に困った事になっちゃいますね。まあ、そういうやつは多い事は確かですね。
稲見
じゃあ、亜星さんご自身は?
亜星
私もバツイチですから。(笑)
自分を弁護するわけじゃないですけどね、確かにそうじゃなくても、ある自由・・・どっかにエゴイスティックを持ってないと実際問題むずかしいと思いますね。
稲見
じゃあ、二足のわらじというのは履けないものなんですかね。
亜星
いや、だからね、ぼくは外国のえらい作家や監督なんかの伝記とか読んでるけど、なかなか優しくて両方をうまくコントロールなさって、非常に人間的な幅を持ってるんですよね。ちょこちょこそんな不良行為するんじゃなくて。そういう人が偉大な人だと思う。でも、モーツァルトなんかろくなもんじゃなかったし。アマディウスっていう映画で、それは一概に言えないですよね。それで、優しくて人間的格が大きくて、社会生活もきちんとなさって、しかも優しくてほんとに素晴らしい。そういう人もいますから。ただその、人間として自由という事は非常に大事かなと思いますね。
それと、少年時代か青年時代に持った理想というものを無くさないという事が大事なんですね。ま、こう言ったら女性の方に悪いんですけど、女性の方の方が早く無くすような気もしますね。
稲見
そうですね、現実的ですものね、女性は。
亜星
福沢諭吉先生が、あの一万円札の・・・なんか同窓会で昔、熱海の方で宴会をやったら、その旅館の主人も慶応の人だったんですね。福沢先生が君達勉強続けてるかね、と言ったら、いや、もうこういう旅館業になっちゃっていそがしくてもう、このごろとんとと言ったら、烈火のごとく怒ったっていうんですね。一生勉強しろって言っただろっていうんですね。そういう事をよく習いましたけどね。やっぱり一生自分が理想を持ったものを追求してって、やっぱり、音楽なんかでもね、もうある程度修めちゃったらもう勉強しなくなりやすいんですね。ある年齢になって。それがだめなんですね。一生こう、道楽なんだから。道楽だったら一生続けていかなくちゃ、努力なしで。そりゃもう何も苦しくもなんともないわけ。もっともっとわかんない事を解明したり、新しい方法を考えたりね。もう毎日それで生きてるぐらいで人間いいと思うんですね。好きな事を。
稲見
亜星さんもまだ勉強を続けられていらっしゃるんですか?
亜星
もう勉強と思わないですもんね、もう道楽だから。
稲見
ほんとにじゃあ、天職でいらしたんですね。もう
亜星
それがね、天職と言われると困るんですけど。ほかに何もあんまりできないですね。だから役者の仕事させられるのは・・・・貫太郎・・(笑)
でも、あれやってるとね、なんていうか音楽の仕事がしたくなりますね。あの後。(笑)
でまたあの音楽ばっかやってるとたまに、なんかああいうふうにドラマでもでてみたいなあと思うからね。木々高太郎っていう方が推理作家がいましてね。その人が慶応の医学部の精神科の教授だったんですね。推理小説もなかなか売れてた。その方は机を2つ持ってるんですね。小説家の仕事をしてる机と、医学の研究する机とね。こっちが飽きたらこっちと、こっちが飽きたら・・・それが一番いいんだって何か書いてらしたのを読みましたけどね。あの一番いけないのはね。疲れたって休む時に、畳の上にねっころがって何にもしないでいる。これはね、疲れがとれないんだっていうんです。精神科の教授だから、まあ、あってるでしょう。(笑) それよりね、気分転換して他の事をもう一つなんかやる。その方がずっと疲れがとれると書いてあって、確かにそれはねそういう部分があるんだと思いますね。
稲見
それじゃ音楽という再確認をするためにああいった役者さんをされてるっていう
亜星
ま、そのためにやるわけじゃないんですけど、なんかむりやりみんなにね、変な方向に。(笑)
小林亜星さん対談トップへ
稲見
自由人であれっていう事はよくわかったんですけども、先ほどの左脳右脳の事なんですが、右脳を鍛えるためには、私達のような者はそういう事をすればなれるんでしょうか?
亜星
そうですね、あの、私達のと言われると困るんだけど。ぼくもたいしたあれじゃないんですから。
やっぱり、右脳は本能を司るものでね、左脳は律の脳って言われますけどね。だけどね、昔からあの、たとえば、ど演歌でメロディしか作れない方がいらっしゃるでしょ。べつにその人を軽蔑してるんじゃなくて。そういう人はね、アメリカではコンポーザー作曲家とは言わないんですね。ソングライターっていうんです。コンポーザーっていうのはね、その音を構築できて、オーケストラが書けて、そういう人をコンポーザーって言うんです。
厳然と区別されてるんですけど、日本では全部作曲家になっちゃう。
で、その、ど演歌が悪いっていうんじゃなくて、それは本能的な民族の血を受け継いでるものですね。こういうものしかできない人は、えー、こういうものがうまい人は編曲とかが下手ですね。ほとんどできない。
で、こんどは、編曲がうまくてオーケストラの伴奏書かしたら上手だっていう人はなかなかこんどはメロディが・・・。どうしてああいう音楽やる人がメロディこんなのしか作れないのかなと思うような。作っても下手ですね。言葉は悪いけど。やっぱり普段ね左脳ばっかり使ってるとね、右脳が退化しちゃうんですよ。それはね。ぼくも最初アレンジの仕事ばっかりやって、これはまずいな、こういう事してるとと思って、途中でやめましたけどね。だからね、ずっと右脳ばっか使ってると、右脳が非常に優秀だとね、左脳も使わないで本能ばっかりで物を作って、退化しちゃうんですね。ほんとのコンポーズ、音楽ってのは左脳と右脳のバランスが非常によくとれた人、たとえばベートーベンとかモーツァルトにしても非常によくとれてるんですよ。だから、ショパンなんかだと、メロディーだけ聞くとね、非常にセンチメンタルで、なんだこれたいしたメロディじゃないなと思われるかもしれないけど、最高の左脳を使って、最高のピアノの技術を使って音楽の方法論でアレンジしてるからこれはまた素晴らしいんですね。だから、大作曲家っていうのはみんな左脳と右脳のバランスが非常にいいわけですね。
稲見
じゃ、亜星さんも?
亜星
いや、わたしのは大は付きません。台無しの台だ。(笑)
小林亜星さん対談トップへ
稲見
どのようにしたらバランスがとれるようになるんですか?
亜星
ぼくもね、考えてたんですけど、認めないというか、そんなのインチキ臭いなと思っちゃうとだめなんですね。私の家内もね、親父さんが技術屋で、兄弟も技術屋さんが多いんですけど。その人がね、「お前の亭主はいいなあ」って。え、何でだよと言うと、「こっちの仕事はコンマ1ミリ狂っても、もう大変な事になるんだぞ」なんてね。まあ、そう言われりゃそうだなと思いますけどね。ずいぶんいいかげんな仕事なのかもしれないけど。でも音もね、半音間違えて書いたら全部変なになっちゃいますからね。
稲見
そうですよね、ずれが・・・
亜星
ええ。そういうとこは似てるんだけど、編曲の場合非常に数学的に理解される方があるんですが、数学的に成り立っている事は確かなんですね。倍音の法則で。それがハーモニーの理論なり、いろんな技術になってるんですけど。そういうものもある程度理解できないと、コンポーザーにはなれないですね。それで、大体仲悪いんですよ、編曲、オーケストラはできなくてメロディしか作れない人とね、編曲ばっかりやっててメロディが作れない人と。大体こっちの人から頼まれて、それを請け負ってやるわけですから。で、あんまり仲良くないけど仕事はしなきゃいけないわけですね。それで、そっちばっかやってるとね、こっちが、かたっぽがだめなんですね。ま、そういう才能の違いもありますね。どっちに向く人かっていうね。
でも、かたっぽをばかにしているといけないんで、そのー、右脳を使うって事をね、軽視してたんですよ。20世紀っていうのはですね。進歩の時代で、ある音大の今は亡くなりましたけどね、昔の学長さんでこの人ドイツで博士の称号を取って非常に素晴らしい方なんですけど、音楽評論家で。この人が大学院で使うベッヘル法という教科書出してて、ぼくもそれ読んだ事ありますけどね。どういう事が書いてあるかというと、音楽には3つあるっていうんですね。
1つは、ホモフォニーの音楽。ドイツの前の音楽みたいな、メロディが一つあって、それにハーモニーやリズムがある。そういう音楽ですね。
ポリフォニーの音楽ってのは、バッハみたいに2つ以上の対のメロディが絡んでる。2つ以上のメロディが同時に鳴ると音楽になる。そう言う思想の音楽。
あと、ヘテロフォニーの音楽ってのがあって、これは1つしかメロディがなくってみんながそのメロディを、斉唱ですね。日本の長唄なんかも聞いてると、三味線でこの、だいたい歌のメロディをなぞってるんですよね、あれ。よく聴くとかざりがついたり、ひきわけたりしますけど。大体民族音楽ってそれが8割なんですって。
でヘテロフォニー音楽を軽視したから、20世紀の音楽は疲弊したって書いてある。これ、その通りなんで、メロディを軽視した事で20世紀の音楽、現代音楽がつまらなくなったんですね。で、12音音楽とか色んな技法でシェーンベルグとかああいう人が考えた音楽、ま、非常に高度な、ある意味では音楽ですけど。なんか、わけわかんない音が新しい音楽だと。
で、どうしてそうなったかというと、20世紀っていうのは、進歩思想の時代だっていうんですね。私もそう思うんですけど。共産主義から始まってマルクスとか、経済原則で人類は進歩した。ああなんなきゃいけないというユートピア思想ですね。それから音楽の方も、人がこういう曲をやったからそれを真似たんじゃいけない。次の技法を開発してやんなきゃオリジナリティが無いと、どんどんどんどん進歩するんだって。そういう考えですね。
その進歩思想に操られてっていうか、追っかけられて音楽とかあらゆる文化が作られてきたのが20世紀じゃないか。ってんですね。進歩しなきゃいけないっていうんですね。そのくせ20世紀が一番人類が人殺しをしてんですね。2000年の昔で一番。
そういう時代で、この、進歩しなきゃいけないっていう恐怖感っていうの、ぼくは、これが21世紀って、そういう思想じゃいけないんじゃないかって思うんですね。
新中世っていうか、そんなの生意気ですけども。生意気と言いながら言ってる。(笑)
ルネッサンスもあっていろいろあったけど、20世紀になってからですよ、この技術の進歩といっしょにあらゆるものが進歩しなきゃいけないと思いだしたんですね。で、それをやってると・・・・
音楽でもね、例えばヨハンシュトラウスの技法でですね、何にも技法変えないでもっと、ヨハンシュトラウスよりもっといい音楽作ってみんなで楽しんだっていいわけじゃないですか。もうヨハンシュトラウス500曲作っただけでもういいやってんじゃなくて。それはね、かまわないと思うんですよね。
メロディを要するに軽視したっていう事は右脳を軽視してる事で、メロディは右脳からしか出てこないんですよね。左脳から作ったメロディってのは、これはね、つまらない。理屈だけで。20世紀の音楽ってのは現代音楽はそれだったんで、疲弊したってんですね。
どうしてそう言うかっていうと、ハーモニーとか、オーケストレーションって楽曲をブレンドする技術ですね。それとか、対位法っていう2つとか3つのメロディを重ね合わせる技術そういうのは勉強して、上野の東京音大の作曲科で教えてますけどね。でもメロディの作り方、しかも人に喜ばれてヒットするメロディの作り方、っていうの教えてる所はどこにも無いわけです。何故無いかっていうと、理屈が無いからですね。これはだから左脳じゃ理解できない分野なんですね。もう左脳からは絶対出てこないものですね。目的というその人の持ってる人生観や今までの経験が全てその、それを人に伝えるって事が目的で、基なんですよね。そっからメロディが産まれてくるんで。
だから、音楽っていうのは非常にオカルト的な部分があるんですね。非常に。メロディは理屈が無いから軽視してたんですね。そういうものは、なんだそんないいかげんなね、どっかから来るなんて新興宗教の念仏みたいなね。ただ、これは気ぃ入れて、もう全身全霊で作った。って言っても、何でそんな事言えるんだってなっちゃいますからね。ところが、祈りが無いとあたらないんですよ。
ぼく、浜圭介と仲いいんで、よく彼も色んな作り方するねえっていうんで。やっぱそういうね、いいメロディっていうのは自分が作ると思うとだめなんですね。この宇宙でね、いいメロディってのは神様が作って漂ってるって。感じとして。それを盗作するって。人のもんじゃないですよ。神様ですよ。だから浜君がいつも今から作るっていう時にね、神に祈ってね、いいメロディ・・・祈るっていうか、ようするに何か浮かんでくるね、ま右脳が働いてるんでしょうね。とにかくすごい高くて宇宙からね。極端に。そういうものが右脳の活動で、これ理屈で説明できたら右脳じゃなくなっちゃう。
だからオカルト的だっていうのは、例えばね、音楽なんかが、初恋の人と若い頃ね、一緒に歌った歌なんかあるでしょ、それを何十年経ってからまた聞いたり歌ったりすると、まざまざとその頃の当時二人の切なかった気持ちとかよみがえってくるじゃないですか。あれ、不思議でしょ。もう昨日のように。そのうちまじまじと感じられてくる。音楽ってそういう不思議なもんなんですよ。もう一種・・・・ん〜そう言ってはいけないけど、オカルト的な、なんか摩訶不思議な分野なんですね。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
もう理屈で言い表せない?
亜星
ええ、そうです。その勘ですね。その第六感みたいのね。これが人に受ける、これが人に喜ばれる、感動されるぞって事を与えるには、自分がその気んなんなきゃね。あのー、浜君じゃないけどね、例えば気持ち悪いんです。ぼくが魔法使いサリーちゃんとか、ひみつのアッコちゃんとか作る時ね、自分じゃ、アッコちゃん、サリーちゃんにね、つもりになってる。(笑) ね、不気味。(爆)
そうなんないとね。
稲見
舞い降りてくるんですか?アッコちゃんとかサリーちゃんが。
亜星
ええ、そうなってないと。だから人に見せらんないですね。(爆) もうそのつもりになってるから。だからぼくの息子達は音楽なんか全然やりませんでしたよ。あんなくだらない馬鹿みたいな親父・・・・そんなね、見栄も外聞もなくね、そうなんないと。
その気になれるって事が重要なんですね。あのー、ちょっとね、詐欺師的でね、不良行為なんですけど。ある意味じゃ。
その人になり切るってのがね、いいかげんな奴じゃないとね、自分をあまりにもしっかり持っててね、そういう人はなれないでしょうね。
そういう自由を保つっていうのはね、普段はちゃんとした生活者で、いいお父さんでいいけど。それをどっかでね、インチキなとこがあってね、すぐそういう気になれるっていうね、そこがひとつの自由さですね。それがなかなか社会生活の適合性無くてね。
稲見
もっとなんか集中して作曲〜って仕事されてるのかと思いきや、遊び心があって、ひらめきのお仕事されてるんですね。
亜星
そうですねあの〜、遊びになって自分が楽しく作って無いと人が楽しんでくれませんよ。
苦労してさ、なんか小説家なんかが彫刻刀・・・ノミの跡を残さずって言いますよね。苦しんだ所が見えてきちゃったら、誰も楽しんでくれないですね。楽しく作るから、遊び心で作るから、人も楽しんでくれる。だから、ぼくらプロの人ってわりと曲を作るの早いんですよ。ぼくの事務所の新入社員が・・・・昔ね、どっかから電話かかってきて、亜星さんに曲をお願いしたいんですが、どのくらいの日数で作っていただけますか?って言われて、なんか、いつも2時間ぐらいで作ってますよ。って言って、そんで他の重役がもうお前はクビだ!って言ってね。そんな馬鹿な事言ったら、金がもらえねぇじゃねえか。って。(爆)
まあ、そんなもんなんですね。プロの人って、普段考えてんですよ。今の時代とかね、どういうのがヒットするか、時代の風潮とか。だから、机に向かったら早いですけどね。
アマチュアの人はわりと普段考えてないで、いきなりそこで考えて物作ったって、長くかかっていいものが出て来ないですね。
佐藤よしろうさんがね、漫画家の、前おっしゃってたけど、連載漫画をね、毎日書いてるのね。何がうけるかって、そういうキャッチボール毎日やってるもんだから、一般の人達とね。それがね、3日もね、風邪かなんかひいて休んじゃうとね、もうどうやってうけていいかわかんなくなっちゃうって。それ、確かにそういうもんですね。毎日作り続けている時ね、忙しいと一番、返ってヒットがでるんですよ。もう分かってますから、どうやったらうけるかね。それがしばらくね、年取るとそんなに仕事がないでしょ。しばらく無いとね、昔は毎日飲んで3曲4曲作ってたのがね、そういう時の方があたるんですね。暇んなるとね、今度はもう宇宙の事から考えてね、こんなつまんない曲作ろうっていうから大変なんだ。暇が無いとね、必要最小限度の事しか考えないから、もう時間が無いから、一番シンプルイズベストで、いい考えが浮かぶんですね、これ。皮肉なもんで。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
じゃあ、曲作りのために、いろいろ雑誌を読んだりとか、マーケティングをされたりとかいうことは?
亜星
そういう事は無いけど、感覚的に、まあ散歩したり、よく渋谷の方とか原宿の方ね、ぶらぶらしてますね。徘徊ね。
稲見
じゃその中でちょっとこう、フレーズがうかんでというような?
亜星
あのね、ぼくらの仕事・・・・作曲やってるプロの人はだいたいそれが最初の訓練なんですね。あの、メモんなくていいっていう。いい歌が浮かんだらね。あ、これいいなって思ったらね、もう、別に忘れないんですよ。家に帰って忘れたらプロじゃない。それが訓練なんですよ。何曲も何曲も書いて。それで、頭の中で直すからね、将棋指しと同じですよ。
だから、亜星さんピアノ弾きながら作るんですか、とか色々言われるけど、ぼくはピアノ弾きながら作ん無いですから。
普通作曲というと、メロディをまず考えると、2小節作ったら次はどういこう?と、こういうのが一番だめなんですね。
まず、全体像が浮かんでくるんです。今作らなきゃならない曲の。この全体像は、今の時代にマッチしてる。求められてる。という事にきっとなるから。この全体像をうかばしてから、だんだんともうほとんど出来て。どうしてもピアノに最初座っちゃうとね、伴奏が無きゃ面白く無いメロディが出来ちゃうんですよ。
これが危険なんですね、そうすると当たんないです。
だからね、どうしてかっていうと、歌ってのはね、やっぱり基本的にねぇ、今はもう再生装置がいっぱい発達してるからウォークマンもいっぱいありますけど。あの、口笛吹いたり、歩きながらねぇ、ハミングしたり。そうやってメロディだけでも魅力が無きゃだめなんですよ。そういうメロディだけで成り立つものがいいメロディで、ヒットする曲なんですね。
それにいろんなアレンジの事考えるのは、後で。出来あがってからで充分で少しメロディ直したり、コード進行直したりね。そういうにするわけですね。だから、まずその全体像と、どういうのかなあ、これはどういうイメージか、浮かんできて、細部がわかってきて、から、かかれんじゃないですか?だから、このね、ここんとこだけ最初浮かんで、次どうしようかな?ってね、そういうんじゃだめですね。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
じゃ、詩が先に決まっててその後にメロディを付けるっていう事は、無いんですか?
亜星
だいたいぼくは、どっちもやりますけど、詩が先に決まってるのが多いですね。
稲見
その詩がどうも自分の感性と合わないという事は?
亜星
それはありますね。(笑) ええ。
稲見
その時はどうされるんですか?
亜星
あのね。だからね。例えば、ヒットってのはね、自分一人じゃ絶対出せないんですよ。ってのはね、作詞家がいるでしょ、それからアレンジャーがいいアレンジして、もちろんメロディ作ってる人もいる、それから歌い手がもう最高によく歌って、それから宣伝部のやつがね、いい宣伝をしてくれる、それからミキサーとか音作りをする人がちゃんとよくやってくれる。全部が100点ないとヒットしない。
で、だれか一人さぼるとね、そこでね、だめになるんですよ。みんなが努力しないと。だから非常にヒットってのは難しいですね。
だから、ぼくが例えばこの詩面白くないや、もういいかげんに書いとけって思ったら、これ絶対ヒットしない。ところが、そうはしてはいけないから、その自分をだますっていうか、いい詩じゃないなって思っても、それをまた、何て言うかな・・・でも、これをどういうつもりでやってんのかな、この詩はなんとか自分の曲の力でよくしちゃおうと。もうそういうふうに思わないとね、できないです。責任あるし。もう一人三振したらこけちゃうんですから。
昔はね、ぼくらがあの、コマーシャルなんかやるテレビの仕事だと、色んな企画なんか持ってくるでしょ。で、だいたいプロデューサなんかと打ち合わせして、今度こういうのやって、世の中をね、あっと言わしてやろう!とか、押し入れん中で爆弾作ってるようなね、そんな雰囲気でやってくんですね。んで、これだ!この企画だよって一人で狂ってるやつがいてね、5人で企画会議して、後の4人が、何これ?こんな事危なくてできないよ。当たらなかったらどうすんだ?って言っても、一人がね、いやっ、これだこれだ!って言い張るとね、5人でやって、一人が20点出したとしたら、20%は売れるんですね。これけっこうヒットなんですよ。
ところが今はね、ぼくらがそういう風にやってる。例えば流行歌作る時とかね。前はそれで成功が、今はコマーシャルなんかで企画会議から相当にして違う。どうしてかって言うとコマーシャルなんてのは、商品ってのがあって、それから何らかの感動をむりやり作り出して、で人を動かして商品を動かして、これ、お仕事なんですね。だから油絵描いてるわけじゃなくて、ポスター描いてるんですよ。
だから、ポスター描いてる目的があるんですよね。それで企画会議から物が出てくる。それで何らかの感動、擬似感動を作り出さなきゃなんですね。そりゃお仕事ですから。
で、コマーシャルから面白い歌やっぱり出るね、どうやってやってるの。ってレコード会社に最初聞かれたんですよ。「いやいや、こう」って、「そうか、そうやって作んのか」ってんで、昔レコード会社の人、専属の人と伊豆の方旅行行ったら、こういう曲が浮かんで、こういう曲誰に歌わせよ?これだ。あの人がいいでしょ?って言ってね。そうやって行ったんですけど、今は歌手自体が商品になっちゃって、この歌手を売るために、コマーシャルとおんなじですね。で、どういう企画で行こうかとなって、それにはこういうメイクで、こういう服装さして、こういう詩にして、こういう詩だったら、あいつがうまい。あいつだ。それから曲はだいたいこういう、アレンジャーも連れてくる。みんな企画会議から出てきて、商品を売るためのものになっちゃったんですね。作曲も作詞も編曲も。
それでその企画会議がね、今はあんまりね、何とも今の時代はね、責任とる人がいないのね。なんか言葉に現れてるもん。「っていうか」とか、なんか自分でこう「なんとかみたいな」と言って、責任とらない言葉になっちゃってんのね。そういうのが出てくるから、みんなが、ま、20点でもいいか。ってやるから、売れない。
一人狂ってる奴がいると、他の奴が反対してそいつが「俺の責任でやる。」とか部長が「じゃ、俺が責任取るからやってみろ。」ってね、こういうのが当たるんですよ。不思議だけど。この感がね、理屈じゃなく、確信してる人がいるとけっこう当たるんですね。
ただ、企画会議でこうなったから、ま、とにかく行ってみようか。これは当たらない。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
誰か言い放つ人がいないとだめなんですね。
亜星
それにはそういう土俵が無いと言え無いからね。この頃それが日本のね、あらゆる分野でヒットが出にくくなってる。
稲見
そうですね、最近そういうヒットCMソングっていうの、あまり聞かなくなりましたよね。
亜星
そうですねえ。それでね、全部企画会議で作ってて、何て言うかなあ、歌手も売るためのものじゃなくて、逆なんですよね。いい曲があって、これを誰に歌わせようかがほんとなんで、この歌手のために作るって本末転倒なわけで、そういう本末転倒になっちゃうと、なかなか大した曲が出なくなっちゃう。で、そういううのまたひっくり返って、違う時代が来るんじゃないかと思いますけどね。
稲見
亜星さんが、変えてください。音楽業界を。
亜星
いえ、ところがね、ヒットが出るためにゃね。全然別の事言うけども。与党になんないと出ないんですよ。例えばね、その業界に文句があったり、今やってる事が面白く無い。こんなんじゃだめだって思ってるからヒットが出ない。今の状態を俺が背負って立つと。与党になんないと。
稲見
当事者意識。
亜星
そう。与党になんないとなかなか出無いですね。
ま、ぼくは今文句があるから、あんまり出ない。(笑) 歳で、いいや。(笑)
小林亜星さん対談トップへ
稲見
どういう風に変えていきたいと思われますか。亜星さんが当事者になられたら。
亜星
そうですね、ぼくは、あのー、2つありますけど。一番アメリカなんかはそれが非常にうまく行ってるようなんですけど。若い新人がですね、出やすいですね。
どうやってその業界に入って行っていいか、わからない。才能ある人はどんどん発掘できて、どんどん出られる。そういう風になってないんですよ。なかなか。
結局つぶされたり、食い物にされたりね。変な話。それで、才能あったのに、もう歳が歳で。それから、歳とった人でも、才能ある人いっぱいいるんだし、そういう人があんまりこう、現役を守りすぎてね、新しい人が入ってくるのを参入を邪魔しちゃったり、そういう事が良くないんで。それでも歳取った人もハリウッドなんかでも、80才でもちゃんと監督してる立派な方が沢山いらっしゃるし、音楽でも。特に年俸の違いとか抜きにして、ほんとにやれる人、才能ある人をどんどん伸ばしたい。今でも運とか奇跡もずいぶんあるし、そういうシステムが無いので、発掘する。
今、音楽産業も何兆円産業になってる、すごい経済になってるのに、ハードはものすごく発達しましたけど、そのハードをになうだけのソフトを作る才能ってのが、すごい枯渇してんですよ。それで、ぼくが学校やってんですけど。
政府なんかがそういう学校作って、現役の先生が教えられるといいんですけど。現役の人は教員免許持ってないから、学校法人になれないから、なかなかね。文部省の件もあって教えられない。
でそういうのをね、それだけの厚さで日本の音楽を輸出したい。音楽に関しては輸出ってのあんまり無いでしょ。あの、スキヤキぐらいしか。あの上を向いて歩こう。
稲見
輸入は沢山ありますけどもね。
亜星
輸入超過ですね。ほんとに。(笑)
ま、そういう夢がね、実現するのはやっぱり国なんかがほんとはやんなきゃいけないけど、たかが、ぼくなんかの力だけではなかなかね。難しいですね、そういう改革するってのは非常にぼくもいっしょけんめやってるんですけど、なかなか進まない。申し訳無い。
何て言うか、日本人ってけっこう、自分達の村には天才なんかいるわけないと思うんですね。そういう意識があるんです。で、やっぱり島国根性って言うか。ひとりでもって水ひとりじめされたんじゃ困る。みんな仲良くやって。ねえ。働き手も稲作ん時いっぱいなきゃいけないし。狩猟民族とそこがちょっと違うと思うんですよね。だから、どうしても、オラの村に天才なんかいてもらっちゃ困るんですよね。そういう小さな考えをみんな無くしてもらえばね、いい人がどんどん出られる世の中になるんですよね。
それがね、平等、平等平等って言いすぎちゃったんですよね。平等なんてね、有り得ないんでね。なんかね、この頃運動会の1着2着が無かったりね。今ね、ドラマもやらないですよ、学芸会で。白雪姫がなんであんな子で、うちの子はなんで魔法使いのばばあなんだって。(笑)
で、みんなで踊ろうっていって、あの子が先頭で、うちのがなんでビリなんだって。しょうがないから輪になって踊ろうって。(笑)
あんなね、学生社会ってね、あんたみたいな美人とね、そうでない人で相当違うしね。
勉強できる優秀な人と、それほどでもない人も相当違うし、でも、運動会ってのはなんかそういう人がね、ものすごく脚光あびたり。みんな違うんだもん。
で、平等ってのはおかしいんで、ぼくはね、公平って事がいいと思うんですね。才能のある人は取りたてる。無い人は、また別の面で。それがね、平等なんて言うからね、これは、平等って良く無いですよ。才能ある人を取りたてないで、無い人と平等なんて。公平がいい。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
じゃあ、今のリストラなんて大賛成ですか。今リストラ世代と言われてるじゃないですか。
亜星
いや、その話になると、ぼくは経済人じゃないから。(笑)
リストラってのは、悲しいね。アメリカ競争社会のね、ぼくなんかが言う事じゃないですけど、原理ってのは、日本人には合わないですね。国際競争化の時代なんて言うけど。ヨーロッパなんか、ファミリーシステムですね。会社が。例えばイタリーとかね。ユダヤ系。
イタリーって言うと何ですかね。ラテン系ですか。
ラテン系、ユダヤ系、中国系ってのは、だいたいみんなファミリーですね。アングロサクソンのドイツ、アメリカは、とにかく株式会社。日本もね、ほんとはファミリー民族だと思うんですけど、戦後アメリカの真似してとにかく、無理矢理資本主義的なものになっていったでしょ。こうなってくると、世界中何百億っていう金が一度にびゅーんて動くような、恐ろしいようなのね、向かないんじゃないの?だから、ファミリーに向くんじゃないかとぼくは思いますけどね。
イタリー人ってすごく、イタリーって国は貧乏だし、政府も金がない。企業もたいしたの無い。でも、生活がすごく豊かですよね。昼んなると飯食ってワイン飲んでシャワー浴びてね・・・(笑)2箇月も休めて。あーいうの羨ましいですね。
なんか、音楽を作るのも、車を作るのも、目的は人生を楽しくするためのものでしょ?なんかね、人生を不愉快にするものをいっしょけんめやる必要は無い。人生を楽しくするという事をするには、自分達も楽しく生きなかったらね、そんなの作るの上手にならないですよ。やっぱり、イタリーのデザインって、いいじゃないですか。やっぱり陽光の下で楽しんでるなって、お酒のひとつでもね、感じますよね。
ああいうラテン的なの、なかなかいいなって。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
学校で、数々の生徒さんがいらっしゃると思うんですけども、亜星さんから見て、あ、この子は才能無いなって方がいらっしゃるわけですよね。
亜星
そこですね。ええ。
稲見
(爆)そ、そういう・・・・
亜星
ぼくはね、最初から言っちゃうんです。あのね、このままここ行ったら、自分がどのくらい差があるか判るから、はいんなさいって。同じ音楽好きな人が入って来てるわけでしょ。今までうぬぼれてて、学校やなんかですごいすごいって言われて、この学校へ来て隣を見たら、やつの方がもっとすごい。自分がどの程度だかわかる。それから、もっと自信持つかもわかんない。おれはなかなかのもんだよって思うかもね。
ぼくも学生時代よその学校に音楽やるやつ、どんなやつがいるか大抵知ってましたよ。その頃から。で、そいつらがプロになってるから、「どうして亜星さんいろんな作曲家みんな知ってるの?」「いや、もう学生時代から知ってるよ」高校時代から知ってますもんね。
あそこの学校にああいうやつがいるってのをね。
だから、それとおんなじで、音楽なんかも一種のファッション的なとこがあるから、他のジェネレーション、世代ってあんまり関係無いんですよ。自分の同じ世代でどんなやつがいるかで、競争相手が決まっちゃうから。他の世代でどんなえらいやつがいるか関係無いんですよ。音楽って世代のもんですから。そう言ってしまうと。
それと、自分がどの程度かわかる。だから、その時「あ、自分はだめだ」と思っても、音楽は趣味と道楽で、一生これね、音楽を友として過ごす人生とね、全然わからない人生とはね、全然違うから。それはやめないで。だけど、人生一番、これは誰かのね、聞きかじりですけど、「人生悲しい事は2つある」それはね、ひとつはね、「初恋に敗れた時。」もうひとつは、「自分が才能ある。好きだと思ってた事に才能が無いと判った時。」この二つは、そのあきらめる時の瞬間ね。だから、ミュージシャンもやめたって。
やめたと思う事は無い。それをね、楽しめばいいんだと判った時ね、あの、リリースされて、デビューして、なんか大物になろうと思うからあれだけど。一生楽しんでいけばいいんだと判った時がね、楽になるんですね。
稲見
それでいい曲がもしかしたら?
亜星
そうすると逆にね、才能が無いかと思ってたけど、いいのができたという事があるんですよ。やめる事は無いですね。
小林亜星さん対談トップへ
稲見
お話をうかがってますと、音楽というのは、マニュアルではほんとに計り知れない部分がかなりあるんだなという事がわかりました。理屈じゃきっと説明できない。
亜星
そうですね、左脳を使うのが編曲とか。だからメロディってのはね、音楽作るっていうもんですから、右脳でしか出てこないんですけど。あのー、メロディーって例えば人間の体みたいなもんですね。これはほんとに変な話ですけど、いい体がね、すばらしい美人ができた。これは、あらゆる年代に、年に関係無いですね。そういう核なんですよ。その核を作るのが一番大事なんです。
だから、「ナツメロ」なんて言葉がありますよね、「懐しのメロディー」ってさ、NHKが作った言葉だけど。あれきらいなんですね。
あれやっぱりね、アメリカではそういうの「エバーグリーン」って言うんですね。いつまでも緑を失わない。新鮮なメロディーですね。そういうのはね、何年たったってね、例えば「ナタリ〜」だって、むかーしの曲ですね。あの歌ね。あれが、アレンジを施して違うアレンジにして。それが、すばらしい女性にどんな洋服を着せて、どんなお化粧した。その時代の流行で。これがアレンジとかそういうもんですね。ハーモニーとか、どんなサウンドで、どんなリズムで。これは時代によって全部変わるもんなんです。その根幹がメロディで、永遠に変わんない。いいものはいいんです。それを作り出すのが、理屈じゃ作れない。
だからそれを、アレンジを変えて。
日本の音楽がまだ未熟なんですよね。なんでかって言うとアレンジが一個しかないんで。アメリカだとヒットした曲はね、ポールアンカが作ったの、シナトラが歌えば、いろんな人が歌ってる。いいメロディはね、みんなが歌う。全部アレンジ変えて。あと、昔の曲でも、違う曲みたいにアレンジ変えて、歌う。
日本ではアレンジ変えると、カラオケ行って、「あれ?イントロ違うこれ、変なの」なんてね、何これ?なんて言われちゃう。(爆) で、その人しか歌えない。あれはあの人の曲だ、歌われてる曲じゃないんだ。
それをいい曲ならいろんな人に歌えばいいんですね。まだそこまで成熟してないから、ま、それがだんだんするのかなあ?
そういう事もやらなきゃなんないから、音楽界でやる事は沢山まだあるんです。
稲見
課題多いですね。。
亜星
課題多いんです。
そうなって初めて、だから、いい曲を作ってそれをいろんな歌手が歌って、アレンジがみんな違うと。何十年前の曲でも、またそれをリバイバルして、もっと違うアレンジでね。あたかも違う曲みたいに聞かせられる。そうすると豊かな音楽ですね。だから、古いアイデアでも、なかなか根幹を生かすって言うかね、全く新しいものになるわけで、昔そういうつもりで作って、今忘れられてるっての沢山あるんです。いいものがね。
稲見
ありがとうございました。
小林亜星さん対談トップへ
対談終了後に、質問に答えていただけましたので、簡単な断片的なメモしか残ってないんですが、、興味深いお話がありましたので、思い出しながら書いてみようと思います。、 かなり省略、要約をしております。場合によっては聞き間違い等もあるかもしれませんのでご了承ください。
質問
語り手:小林亜星さん
聞き手:稲見幸子さん
質問作成、編集:S.Ogawa
ウエブ コンサート ホール - 楽屋 -
Copyright (C) 2000 Sumitaka Ogawa
小林亜星さん対談トップへ